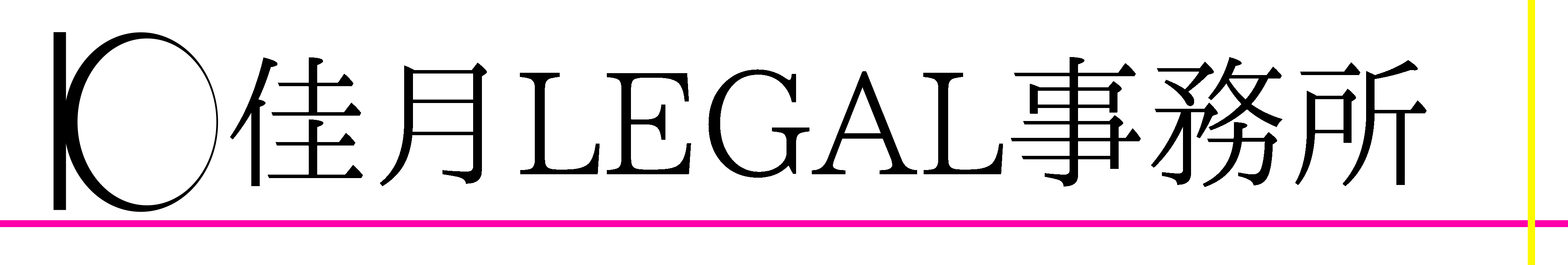知っておきたい相続放棄の手続き
後悔しないための完全ガイド
「相続放棄」という言葉を聞いたことがありますか?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという法的な手続きのことです。
借金が多いなど、相続したくない理由がある場合に有効な手段ですが、手続きには期限や注意点があります。
この記事では、相続放棄の手続きの流れを分かりやすく解説します。(詳細・例外は割愛)
なぜ相続放棄をするのか?
相続放棄を選択する主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人の借金が多い場合: プラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続するとその借金も引き継ぐことになります。
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合: 例えば、事業を承継する特定の子供にすべての財産を譲りたい場合などです。
- 親族との関係を断ちたい場合: 遺産分割協議に参加したくないなど、親族との関わりを避けたい場合。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
主な流れは以下の通りです。
1. 相続の開始を知る
被相続人が亡くなったことを知った時点から、相続放棄の手続き期間が始まります。
2. 相続財産の調査(任意)
相続放棄をするかどうか判断するために、被相続人の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産)を調査します。
3. 相続放棄の申述書の作成
家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を作成します。
申述書には、被相続人の情報、相続人の情報、相続放棄をする理由などを記載します。
4. 必要書類の準備
申述書と一緒に提出する必要書類を準備します。
一般的に必要な書類は以下の通りです。
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が記載されているもの)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の住民票
- 被相続人との関係によって追加で必要な書類(例:被相続人の配偶者や子でない場合は、被相続人の父母や祖父母の戸籍謄本など)
5. 家庭裁判所への申述
準備した申述書と必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
6. 家庭裁判所からの照会
家庭裁判所から、相続放棄の意思を確認するための照会書が送られてくることがあります。
照会書に回答し、返送します。
7. 相続放棄の受理
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄の期限と注意点
- 熟慮期間: 相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
- 期限徒過: 熟慮期間内に手続きを行わなかった場合、原則として単純承認(すべての財産を無条件で相続すること)をしたとみなされます。
- 期間の延長: やむを得ない理由がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長できる可能性があります。
- 相続財産の処分: 相続放棄をする前に、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる場合がありますので注意が必要です。例えば、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却したりする行為はこれに該当します。
- 次の順位の相続人: 相続放棄をすると、その相続人は最初からいなかったものとして扱われ、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子が相続放棄した場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続権が移ることがあります。
迷ったら専門家へ相談を
相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、必要書類の準備や法的な判断が必要となる場面もあります。もし手続きに不安がある場合や、判断に迷う場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、相続に関する重要な選択肢の一つです。手続きの流れや注意点をしっかりと理解し、後悔のない選択をしましょう。熟慮期間は限られていますので、早めに検討することが大切です。
免責事項: このコラムは一般的な情報提供を目的としており、法的な助言を提供するものではありません。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。